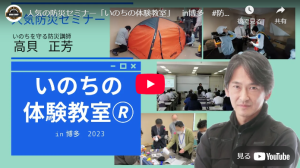内閣府「 ぼうさいこくたい2025 新潟大会」
と同時開催しました。
防災クッキング、防災劇場をはじめとする
楽しく学べる体験型防災訓練 に加え
9月 7(日)日 10:30~12:00
オンラインセッションとしLIVE配信!
浦安警察署の展示や講話。
コスプレコーナー等、開催
★いのちを守る防災CAMP
2025年9月6日(土)7日(日)
イオン新浦安ショッピングセンター
いのちを守る防災プロジェクト実行委員会
フラッシュオーバーと「扉を閉める避難」という判断技術
― スイス火災事故(1/1)を踏まえた危機管理的考察 ―
1.何が起きたのか
2026年1月1日にスイスで発生した火災事故は、「突発的に室内全体が炎に包まれた」と報じられた。
この表現の背後にある現象が、フラッシュオーバーである。
フラッシュオーバーは、火災における一現象であると同時に、
人の意思決定の遅れや誤解が引き金となる危機管理上の転換点でもある。
本稿では、
- フラッシュオーバーの発生メカニズム
- 「扉を閉める」という行為の危機管理的意味
- 避難行動における判断原則
を整理し、生活・施設・組織に共通する知見として提示する。
フラッシュオーバーとは、
閉鎖空間内に蓄積した可燃性ガスと熱が、
ある瞬間に一斉着火し、
室内全体が炎に包まれる現象
である。
重要なのは、
「発生前に、火が小さく見える時間帯が存在する」点である。
この段階では、
- 天井付近に高温の煙層が形成され
- 視界は徐々に悪化し
- 室温は人が耐えられる限界に近づいている
しかし、多くの人は
「まだ逃げられる」
「今なら消せるかもしれない」
と判断してしまう。
フラッシュオーバーは、
物理現象であると同時に、判断の錯覚が生む災害である。
3.「扉を閉める」ことの意味
火災時の行動として「扉を閉める」という助言は、しばしば誤解される。
これは
「扉を閉めてその場に留まる」
という意味ではない。
正確には、
火や煙が発生している「その部屋」を区画し、
自身は反対方向へ退避する
という選択すべき行動原則である。
扉を閉めることには、以下の効果がある。
- 酸素供給を抑制する
- 熱と煙の拡散を遅らせる
- フラッシュオーバーの発生条件を一時的に緩和する
つまり扉は、
火を止める道具ではなく、時間を稼ぐための境界線である。
4.避難行動における判断原則
フラッシュオーバーを回避するために必要なのは、技術より判断基準である。
以下の兆候が見られた場合、
その空間は「使用不能」と判断すべきである。
- 天井付近に黒煙が滞留している
- 熱のため自然と姿勢を低くしたくなる
- 視界が急激に悪化している
この段階での消火行動は、
成功よりも致死リスクのほうが高い。
危機管理の原則は明確である。
「消せるか」ではなく
「戻れなくなるか」で判断する
5.スイス事故が示す教訓
今回の事故が示唆するのは、
フラッシュオーバーそのものよりも、
- 状況が「まだ大丈夫」に見える時間帯
- 判断を先送りしてしまう心理
- 空間全体が一気に危険化する非連続性
である。
これは住宅火災だけでなく、
宿泊施設、福祉施設、事業所など
人が集まる空間すべてに共通するリスクである。
6.いのちを守るために
火災は、炎が人を殺すのではない。
判断の遅れが、人を逃げ場のない空間に残す。
フラッシュオーバーを理解することは、
火災を恐れることではなく、
「避難行動を開始する判断」を学ぶことである。
扉一枚を境に、
生と死が分かれる場面があることを、
私たちはもっと冷静に共有していく必要がある。
講師派遣のお問い合わせ
一般社団法人 いのちを守るatプロジェクトJAPAN
tel:0287-74-5129
e-mail : info@imp-japan.org
https://imp-japan.org
公式LINEコール(無料)QRコードから!
とりあえず聞いてみようと思われた方。
お問い合わせは 公式LINEコールが便利です。
下記のQRコードをスキャンして、ご連絡ください。